×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ラッセル・クロウ監督 『あの頃ペニー・レインと』 2000年

So I called up the Captain
'Please bring me my wine'
He said
'We haven't had that spirit here since 1969'
And still those voices are calling from far away,
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say...
そして僕は管理人を呼びワインを頼んだ
彼が言うには
「1969年よりこちらはその酒を置いていません」
その上まだ、あの遠くから呼ぶ声が聞こえる
真夜中に覚醒させ、耳を傾けるほかないあの声が
上に挙げたのは1976年に発表されたイーグルスの代表作『ホテル・カリフォルニア』のタイトル・トラックのあまりにも有名な一節である。ワインを求める客に対するホテル・カリフォルニアの管理人の返答は、ロックの黄金時代の終焉を告げている。
1973年を舞台にしたこの映画の冒頭、カリフォルニアの街を行く車のなかから眺めるように、同アルバムのジャケットが連想される風景が映される。つまりそれが意味するのは、これは、決定的に乗り遅れてしまった先行する物語に対して抱く年少者の憧憬を描いた映画なのだということ。
主人公のウィリアムは、かつて家を出て行った姉からレコードを譲り受けたことからロックに傾倒した早熟な15歳の少年。ロックへの情熱を共有できる仲間も見つからぬまま、学級新聞等にロックの記事を書いていたところ、伝説のロック誌クリームの編集長と出会い、薫陶を受ける。そこからホイホイと、スティルウォーターという新進のバンドのツアーに同行し、その記事をローリング・ストーン誌に書くことに話が進む。そして彼はバンドのグルーピーの少女、ペニー・レインと出会うこととなる。
彼がロックに目覚めた頃、すでにロックはその輝きを失い始めていた。ウッドストックはとうに終わり、ビートルズは解散し、サイケデリックの花を咲かせた三人のスターが死んでいた。誰もがすでに語られた物語ばかりを追いかけ、夜毎の乱痴気騒ぎのなかでロックは自己パロディを繰り返し、様式化し始めた。
ウィリアムはとうとう憧れの世界に飛びこめたことに舞い上がる。さらに、その世界で堂々と振舞う同年代のペニーに叶わぬとは知りながら想いをよせるようになる。しかし次第に矛盾は蔽い隠すことができなくなっていく。ツアーが終わると二人はバンドを去って、彼は記事を書き、彼女はかねてより望んでいたモロッコへと旅立つ。
それは一見、彼らが自らの新しい道を進むと決めたかのように思える。しかし、ウィリアムは記事を書くにあたってクリーム誌の編集長に助言を求め、ペニーの旅先はヒッピーズム華やかりし頃の聖地巡礼の最もアクセスの容易な土地ときている。彼らは結局、また誰かの物語を模倣/反復しているのだ。そう考えるのはなんとももの悲しくはあるが、いみじくもジョン・レノンの言葉通り、「夢は終わった」ということなのだろう。
時代と青春期に対する懐古の念に満ちた映画だ。
So I called up the Captain
'Please bring me my wine'
He said
'We haven't had that spirit here since 1969'
And still those voices are calling from far away,
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say...
そして僕は管理人を呼びワインを頼んだ
彼が言うには
「1969年よりこちらはその酒を置いていません」
その上まだ、あの遠くから呼ぶ声が聞こえる
真夜中に覚醒させ、耳を傾けるほかないあの声が
上に挙げたのは1976年に発表されたイーグルスの代表作『ホテル・カリフォルニア』のタイトル・トラックのあまりにも有名な一節である。ワインを求める客に対するホテル・カリフォルニアの管理人の返答は、ロックの黄金時代の終焉を告げている。
1973年を舞台にしたこの映画の冒頭、カリフォルニアの街を行く車のなかから眺めるように、同アルバムのジャケットが連想される風景が映される。つまりそれが意味するのは、これは、決定的に乗り遅れてしまった先行する物語に対して抱く年少者の憧憬を描いた映画なのだということ。
主人公のウィリアムは、かつて家を出て行った姉からレコードを譲り受けたことからロックに傾倒した早熟な15歳の少年。ロックへの情熱を共有できる仲間も見つからぬまま、学級新聞等にロックの記事を書いていたところ、伝説のロック誌クリームの編集長と出会い、薫陶を受ける。そこからホイホイと、スティルウォーターという新進のバンドのツアーに同行し、その記事をローリング・ストーン誌に書くことに話が進む。そして彼はバンドのグルーピーの少女、ペニー・レインと出会うこととなる。
彼がロックに目覚めた頃、すでにロックはその輝きを失い始めていた。ウッドストックはとうに終わり、ビートルズは解散し、サイケデリックの花を咲かせた三人のスターが死んでいた。誰もがすでに語られた物語ばかりを追いかけ、夜毎の乱痴気騒ぎのなかでロックは自己パロディを繰り返し、様式化し始めた。
ウィリアムはとうとう憧れの世界に飛びこめたことに舞い上がる。さらに、その世界で堂々と振舞う同年代のペニーに叶わぬとは知りながら想いをよせるようになる。しかし次第に矛盾は蔽い隠すことができなくなっていく。ツアーが終わると二人はバンドを去って、彼は記事を書き、彼女はかねてより望んでいたモロッコへと旅立つ。
それは一見、彼らが自らの新しい道を進むと決めたかのように思える。しかし、ウィリアムは記事を書くにあたってクリーム誌の編集長に助言を求め、ペニーの旅先はヒッピーズム華やかりし頃の聖地巡礼の最もアクセスの容易な土地ときている。彼らは結局、また誰かの物語を模倣/反復しているのだ。そう考えるのはなんとももの悲しくはあるが、いみじくもジョン・レノンの言葉通り、「夢は終わった」ということなのだろう。
時代と青春期に対する懐古の念に満ちた映画だ。
PR
The Oscillation 『Out of Phase』 2007年
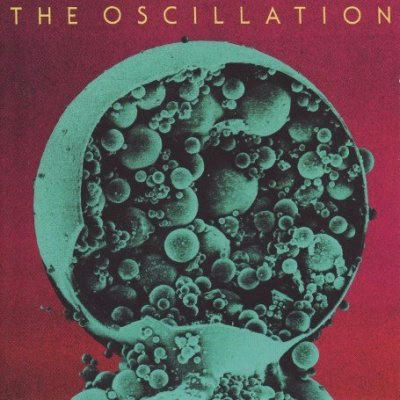
音楽には時を封じこめる力があるらしい。
耳にするたび、それをよく聴いていた当時の記憶、感情や情景、質感、匂いまでを思いださせる曲というのを、だれしもひとつやふたつは持っているはずだ。そうしたものはたちまち人をメランコリックなノスタルジーに浸らせる訳だけれども、まあ過去に埋没するでもなく古い写真のようにたまに開いては楽しむというのがきっと大人の嗜みというものだろう。
ジ・オシレイションのこのアルバムはいかにも暗いエレクトロニカといった内容なのだけど、これが出た2007年といえば僕にとって上京した年にあたるわけで、その年の特に今頃は一人暮らしの寂寥を慰めるためか、そういったエレクトロニカやシューゲイザー、ポストロックなどをよく聴いていたのだけど、その中でも繰り返し何度も聴いたのが、ジュリアン・コープスのカバーだというこの「ヘッド・ハング・ロウ」という曲。あの年の今頃は今年よりもずっと寒くて、よく雨が降っていた気がするなあ。
The Oscillation - Head Hang Low
All is lost
In bright confusion
Once that loss
Was far away
Frightened man
In deep division
Frightened man
With head hang low
すべては失われる
鮮やかな混乱のなかに
いちど失われたものは
はるか彼方
隔壁の奥で
男は怯えている
低く頭をうなだれて
You may sit alone like me
But, please, don't sit alone like me
My world's very beautiful today
頼むから ぼくのように
ひとり孤独に座すなんて真似はやめてほしい
世界は今日、こんなにもぼくに美しいのに
Patron saint
Of lost illusion
Come and paint
My world in grey
I am lost
With no companions
All are bowed
With head hang low
きえ去った幻の
守護聖人よ
ふたたび顕れ、
世界を灰に染めよ
ぼくはひとり
迷いこんでしまった
なにもかもが撓み
低く頭をうなだれている
You may sit alone like me
But, please, don't sit alone like me
My world's very beautiful today
頼むから ぼくのように
ひとり孤独に座すなんて真似はやめてほしい
世界は今日、こんなにもぼくに美しいのに
音楽には時を封じこめる力があるらしい。
耳にするたび、それをよく聴いていた当時の記憶、感情や情景、質感、匂いまでを思いださせる曲というのを、だれしもひとつやふたつは持っているはずだ。そうしたものはたちまち人をメランコリックなノスタルジーに浸らせる訳だけれども、まあ過去に埋没するでもなく古い写真のようにたまに開いては楽しむというのがきっと大人の嗜みというものだろう。
ジ・オシレイションのこのアルバムはいかにも暗いエレクトロニカといった内容なのだけど、これが出た2007年といえば僕にとって上京した年にあたるわけで、その年の特に今頃は一人暮らしの寂寥を慰めるためか、そういったエレクトロニカやシューゲイザー、ポストロックなどをよく聴いていたのだけど、その中でも繰り返し何度も聴いたのが、ジュリアン・コープスのカバーだというこの「ヘッド・ハング・ロウ」という曲。あの年の今頃は今年よりもずっと寒くて、よく雨が降っていた気がするなあ。
The Oscillation - Head Hang Low
All is lost
In bright confusion
Once that loss
Was far away
Frightened man
In deep division
Frightened man
With head hang low
すべては失われる
鮮やかな混乱のなかに
いちど失われたものは
はるか彼方
隔壁の奥で
男は怯えている
低く頭をうなだれて
You may sit alone like me
But, please, don't sit alone like me
My world's very beautiful today
頼むから ぼくのように
ひとり孤独に座すなんて真似はやめてほしい
世界は今日、こんなにもぼくに美しいのに
Patron saint
Of lost illusion
Come and paint
My world in grey
I am lost
With no companions
All are bowed
With head hang low
きえ去った幻の
守護聖人よ
ふたたび顕れ、
世界を灰に染めよ
ぼくはひとり
迷いこんでしまった
なにもかもが撓み
低く頭をうなだれている
You may sit alone like me
But, please, don't sit alone like me
My world's very beautiful today
頼むから ぼくのように
ひとり孤独に座すなんて真似はやめてほしい
世界は今日、こんなにもぼくに美しいのに
星野智幸 『俺俺』 2010年

人間の生活が公私の2面に分けられるとしたら、前者には労働が、後者には家庭が割り振られるのだろう。両者に共通するのは、誰もがそのなかで自分にあてられた役割を演じているということであり、決定的な違いは、その役割が前者では代替可能で後者では不可能ということであろう。しかしこの代替可能性を逆転させて「私」の面へと導入するとどうなるか。
仕事が人間を育てるということは大いにあるらしい。とはいえ、人の個性が決定づけられるのは、基本的には「公」以前に私たちがつねに/すでにそこに放りこまれている「私」の面においてではないだろうか。そうすると、そこでの役割が代替可能となるならば、代わられる私と代わる彼は同じ人物であるということになってしまう。つまり誰もかれもが俺となる訳だ。
道で出逢うのは仏ではなく自分自身であり、自分と対面し、自分を殺せ。かつて岡本太郎は禅僧の会合の場でこう述べて喝采を浴びたらしいが、さすがの岡本太郎も疑心暗鬼となった大勢の俺同士がバトルロワイヤルさながらに殺しあう恐慌状態までは想像しなかったに違いない。その図は凄惨を極める。なぜならそれは、一見淘汰のヒエラルキーを昇っているかのように見えても、結局殺したのも殺されたのも俺であるのだから、殺した俺は殺された俺の弱さをも自分が備えていることに気づかざるをえず、自己嫌悪の泥沼にずぶずぶと沈み込んでいくほかないからだ。
なにかと評判の本書であるが、たしかにこれほど時代に要請されて存在の不安を書ききったものは珍しいだろう。リアルタイムで読むことができたのを喜びに思う。
人間の生活が公私の2面に分けられるとしたら、前者には労働が、後者には家庭が割り振られるのだろう。両者に共通するのは、誰もがそのなかで自分にあてられた役割を演じているということであり、決定的な違いは、その役割が前者では代替可能で後者では不可能ということであろう。しかしこの代替可能性を逆転させて「私」の面へと導入するとどうなるか。
仕事が人間を育てるということは大いにあるらしい。とはいえ、人の個性が決定づけられるのは、基本的には「公」以前に私たちがつねに/すでにそこに放りこまれている「私」の面においてではないだろうか。そうすると、そこでの役割が代替可能となるならば、代わられる私と代わる彼は同じ人物であるということになってしまう。つまり誰もかれもが俺となる訳だ。
道で出逢うのは仏ではなく自分自身であり、自分と対面し、自分を殺せ。かつて岡本太郎は禅僧の会合の場でこう述べて喝采を浴びたらしいが、さすがの岡本太郎も疑心暗鬼となった大勢の俺同士がバトルロワイヤルさながらに殺しあう恐慌状態までは想像しなかったに違いない。その図は凄惨を極める。なぜならそれは、一見淘汰のヒエラルキーを昇っているかのように見えても、結局殺したのも殺されたのも俺であるのだから、殺した俺は殺された俺の弱さをも自分が備えていることに気づかざるをえず、自己嫌悪の泥沼にずぶずぶと沈み込んでいくほかないからだ。
なにかと評判の本書であるが、たしかにこれほど時代に要請されて存在の不安を書ききったものは珍しいだろう。リアルタイムで読むことができたのを喜びに思う。
プロフィール
HN:
tkm
性別:
男性
自己紹介:
東京在住の学生です
アウトプットもたまにはね
アウトプットもたまにはね
つぶやき
アーカイブ
最新記事
(04/14)
(03/23)
(12/25)
(08/05)
(02/07)
